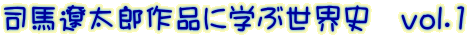 〜『韃靼疾風録』、『項羽と劉邦』、『草原の記』〜
〜『韃靼疾風録』、『項羽と劉邦』、『草原の記』〜
※小説の作品紹介、および作品のフィクション(虚構)度は、『司馬遼太郎読本』(平成8年11月初版 徳間文庫
刊)による。 小説以外については、刊行本の裏表紙の解説などを作品紹介とする。
△=架空の人物が主人公の作品
○=実在の人物が主人公だが虚構の多い作品
◎=実在の人物が主人公で虚構の少ない作品
●=小説ではなく評伝・史伝とでも呼んだほうがいいもの
※ルビについては、引用文そのままとした。ただし、( )の中に示した。また、引用部分の直前に
ルビのあったものについてはそれをつけた。
一、『韃靼疾風(だったんしっぷう)録』
(昭和59年1月〜63年9月 「中央公論」連載 中公文庫)より
作品紹介 日本では江戸初期、中国では明末の時代、韃靼族が中原(ちゅうげん)をうかがい、やがて
清王朝を起こす時代、韃靼国の探索を命じられた平戸藩士桂庄助は、異文化のなかでいか
にして生き、何を考えたか。さらに、庄助と韃靼族の公女アビアとの愛をも描く。司馬遼太郎
最後の長編小説。
フィクション度△ 架空の人物が主人公
韃1 三国時代の朝鮮 「新羅(しんら)、百済(くだら)のラ」
土地の人は、マツラ・マズラと発音する。はるか古代、 『魏志(ぎし)』 倭人伝(わじんでん)の撰者陳寿
(ちんじゅ)は、土地の音(おん)に末盧(まつら)国という文字をあてた。マツラのラとは、おそらく古語にお
いて国という意味であったろう。玄海灘のかなたに古代の耽羅(たんら)国(済州島)がうかび、その北
に新羅(しんら)国があった。百済国をクダラ国などと和訓したことを思いあわせるべきである。
みな、ラがつく。ついでながら、平戸も古代には庇羅(ひら)という字があてられていた。
(文庫上巻10P)
韃2 明代の長城の外の非漢民族 「タタール(韃靼(だったん))部」
じつをいうと、タタール(漢字表記して韃靼)とは、もともとモンゴル民族内部での一部族の呼称に過ぎ
なかった。元以前の宋代の漢民族が、モンゴル人全体を韃靼とよびはじめ、元代ではそのようによぶ
ことをはばかって表面ではそういう呼称をつかわなかった。元がほろぶとき、中国大陸を支配していた
モンゴル兵は、土地に執着せず、風のように騎馬で北の草原に帰って行った。そういうふしぎな滅亡
の形態を当時、北帰とよんだ。明帝国では、草原に北帰したモンゴル人のことを、卑しんで韃靼とよぶ
ようになった。(略)韃靼ということばはいまでは(1)さほどに厳密ではなくなり、地域・人種ともに茫漠
としてきて、長城のそとにいる野蛮な非漢民族のことを一般に韃靼とよぶようになった、ともいった。
(文庫上巻69〜70P)
[注]
(1)作品中では明末(17世紀前半)を指す。
韃3 清(しん)の皇室の姓 「愛新覚羅(あいしんかくら)(アイシンギョロ)のアイシン」
cf.ギョロは「骨族・名門」の意
「アイシン」
彼女の顔が厳粛になった。彼女がいったことばは、 「満韃子(マンダーツ)」 などと蔑称されている女
真人が、みずからの種族をうつくしいものとして自称するときは、そうよぶと庄助はきいている。明人は
「愛新」と表記する。アイシンとは、もともと黄金という意味であるらしかった。
(文庫上巻94P)
韃4 1898年、ロシアが租借した遼東半島南端の地
1904年4月〜05年1月、日露戦争の激戦地・ロシア軍要塞 「旅順(りょじゅん)」
「旅順」
奇妙な地名というほかない。しかし明の船乗りにいわせればごく自然な発想によってつけられた地名
のようで、(略)つまりは、山東を発し、廟島(びょうとう)群島(1)を経、遼東にいたる船にとって旅程の順
路にあるがために旅順という。
(文庫上巻P281〜282)
[注]
(1)渤海(ぼっかい)海峡の南北に連なる諸島
韃5 (後金→)清(しん)を建国した半猟半農のツング−ス系民族 「満州族」
cf.中国東北部(の森林地帯)を指す旧地域名。日本の傀儡国家満州国(1932〜45)の略称
「わしはマンジュ(満州・満洲)だ」
と、かれがしばしば言ったのは、むろん女真族のなかでのマンジュ部族だという意味なのだが、同時
に、文珠(もんじゅ)菩薩だ、という語感を加味させていた。その証拠に、かれは正式の儀式のときや戦
陣では大きな玉の数珠(じゅず)を肩からたすきに掛けていたし、(略)生ける文珠菩薩というつもりであ
った。といいながらヌルハチに仏教の素養があるわけではなく、経典を誦(ず)するわけでもなく、僧を従
えてもいなかった。元来、僧など女真族には存在しない。でありつつもヌルハチがわれはマンジュ(文珠)
なりと呼号しつづけてきたのは、女真族が古来精神的体質のなかにもっているシャーマニズムの上に
乗っていたとみるべきであったろう。(略)
ヌルハチはよく人をあざむいた。文明にくるまれている漢人や朝鮮人からみれば、「黠慧(わるがしこい)」
という評に尽きるが、女真族からみれは智慧の菩薩とされる文珠のように感じられることもしばしばで
あったにちがいない。
(文庫上巻P372〜373)
二、『項羽(こうう)と劉邦(りゅうほう)』
(昭和52年1月〜54年5月 「小説新潮」連載 連載時の題名は、
『漢の風、楚の雨』 新潮文庫)より
作品紹介 中国の秦末の混沌から、ふたりの男がやがて天下を争う。武神の如き強さの項羽と百戦
百敗する劉邦。天下はいずれに。『史記』にも描かれた動乱の時代の著名な人物像を通
じて、“人間の器”とはなにかを考えさせる。昭和54年から55年にかけての大ベストセラー。
フィクション度◎ 実在の人物が主人公で虚構度の少ない作品
項1 秦(しん)の初代皇帝 「始皇帝」
「−あんなやつが」
皇帝か−と、その在世中、巡幸(じゅんこう)(1)の途次かれを路傍で見た多くの者がおもったのは、か
れによってほろぼされた国々の遺民としての感情もあったであろう。しかし一方、かれが中国を統一する
というばかげた、いわば絵空事のようなことを現実にしてしまったことが、ひとびとにかえっていかがわし
さを感じさせる結果になった。第一、皇帝ということばそのものが新語であり、かれ自身が創作(2)した。
言葉がまだ新しくて熟していないのに、実体である皇帝に対する尊敬心の習慣が根づいているはずがな
かった。
(文庫上巻P5)
[注]
(1)君主が方々をめぐり歩くこと
(2)「三皇五帝」伝説から。あるいは、天・地・人を統合する宇宙神とされた泰皇(たいこう)から。
項2 秦(しん)の始皇帝だけが使用を許された一人称 「朕(ちん)」
cf.フランス絶対主義の絶頂期ルイ14世の言葉に、「朕は国家なり」がある。
皇帝一個が、中間勢力なしに宇内(うだい)のすべての人間−中国の人口は五千万(1)と想像される
−に対しているというのは、自信家の始皇帝にとっても多少の不安と肌寒さがあった。ただかれは組
織でうずめようとせず、装飾でうずめようとした。自分一個の存在を厳重に装飾し、いやがうえにも絶
対であることを見せようとした。かれは皇帝という称号もつくったが、かれのみが用いる一人称も制定
した。自分のことを、
「朕」
とよんだ。一人称を専有したのである。
(文庫上巻P8)
[注]
(1)秦の当時
項3 春秋時代の(三国時代の)「呉(ご)」
この叔父とおい(1)が最後に腰を落ちつけたのは、呉中(ごちゅう)(いまの蘇州)の町である。
呉中は春秋の呉国の旧都で、呉国がほろんでからも、単に「呉」といえばこの都市のこと
を指した。はるかな後世、この呉の発音が漢籍や経典とともに東方の朝鮮南部や日本に伝わ
って呉音(ごおん)となり、また絹織物をつくるこの土地の方式も伝わって呉服とよばれたりした。
(文庫上巻P52)
[注]
(1)項梁と項羽
項4 (前)漢の初代皇帝 「劉邦(りゅうほう)」
劉家はごくありきたりな農家といっていい。
「劉」
という姓を持つだけで、その家族たちは名前らしいものをもっていない。当の劉邦でさえ、
邦というのは名であるのかどうか。
「パン(邦)」
は、にいちゃんという方言で、ときにねえちゃんというときも、パンという。劉邦とは、
「劉兄哥(あにい)」
ということであった。
劉邦のおもしろさは、いっぱしの存在になってからも名を変えず、あにいのまま押し通したこと
である。結局、それが名前になった。それどころか、中国史上最大の名になってしまった。
(文庫上巻P74)
項5 渭水(いすい)流域の渭水盆地で、中国古代史上の一中心地。その秦以降の呼び名
「関中(かんちゅう)」
cf.現在の陝西省中部
関中盆地は、この大陸の漢(かん)民族圏のなかにあっては西にかたよりすぎている。そのために
西域への通路にあたり、はるかな西方の文物が流入しやすい点、陸の貿易港という機能をもってい
た。また北方の異民族に対しては蕭関の(しょうかん)嶮(けん)がさえぎり、西は散関(さんかん)がそ
そりたつ。南は武関(ぶかん)がこの盆地を守り、もっとも重要な方向である東方の中原に対しては
函谷関という天下の嶮(1)がこれを守っている。(略)戦国のある時期、秦が都をうつしてこの盆地の
咸陽(かんよう)にさだめたとき、すでに秦の天下制覇(せいは)の条件の重要な部分が成立したとい
えなくはなかった。
(文庫上巻P164)
関中という地理的呼称の語源は、当然ながら関所の内側、という意味である。その関所の代表的
なものは函谷関(かんこくかん)であった。(略)かつて、周(しゅう)(2)もこの関中に都(3)を置いた。
秦帝国もこの地の咸陽に首都を置き、のち漢もここに首都をさだめ、後代、唐の首都長安(ちょうあん)
が置かれるにおよんで関中の全盛期をむかえたが、ついでながら唐の長安のころには秦のころとち
がい、関中の農業生産高が大いにさがって、むしろ食糧を他から移入せざるをえなくなっていた。
(文庫上巻P315)
[注]
(1)「箱根の山は天下の嶮 函谷関もものならず」の歌詞
(2)西周
(3)鎬京(こうけい)
項6 殷王朝後期の首都(商。大邑(ゆう)商)の跡 「殷墟(いんきょ)」
cf.現在の河南省安陽市小屯村が中心
会見(1)の場所は、
「殷墟(いんきょ)(河南省)」
ということに、項羽は指定した。(略)
殷墟とは、古代の殷王朝の遺跡という意味である。殷墟という考古学的遺跡そのものを指す地名が、
すでにこの秦(しん)帝国の時代から存在していたことが分かるのは、『史記』の記載のおかげといって
いい。
(文庫上巻P397)
[注]
(1)項羽に敗れた秦の将軍、章邯(しょうかん)とのもの
項7 秦の都 「咸陽(かんよう)」
咸陽は秦がまだ王国だったころからの累代の都で、九山(きゅうそう)の南にあたり、渭水の北岸にな
る。陽とは、山の南、川の北をいうが、この位置が二つながら(咸)陽であるために咸陽と名づけられた。
(略)始皇帝は中国史上、最初の記念碑趣味を政治の中心にすえた男で、まだ王であったころ、中原の
王侯を攻めつぶすごとにその宮殿とそっくりなものを咸陽に建てならべ、南の方渭水の流れに映じさせた。
(文庫中巻P77)
項8 「漢」
漢中とは、そこを流れている漢水という河の名から出た地名らしいが、その地域は単に漢ともよばれ
ることのほうが多かった。あらたに漢中王になった劉邦に対し、ひとびとは漢王とよんだ。この故秦の
流刑地の呼称が、後代、この大陸のすべてに対する呼称になり、またこの大陸で共通の文化をもつ
民族に対する呼称として二十世紀にいたってもなおよばれるようになろうとは、この当時、韓信もその
女も、あるいは劉邦自身、もしくはその謀臣の張良でさえ夢にも予想できなかった。
(文庫中巻P146)
三、『草原の記』
(平成3年4月〜4年2月 「新潮45」連載 新潮文庫)より
作品紹介 史上空前の大帝国をつくりだしたモンゴル人は、いまも高燥な大草原に変わらぬ営みを
続けている。少年の日、蒙古への不思議な情熱にとらわれた著者が、遥かな星霜を経て
出会った一人のモンゴル女性。激動の20世紀の火焔(かえん)を浴び、ロシア・満洲・中国
と国籍を変えることを余儀なくされ、いま凛々(りり)しくモンゴルの草原に立つその女性をと
おし、遊牧の民の歴史を語り尽くす感動の叙事詩。
草1 匈奴との同族説が有力なアジア系遊牧騎馬民族 「フン族」
私は旧制中学の東洋史で、匈奴のことを、キョウドともいい、フンヌともいうと習った。このフンヌという名称
が、ヨーロッパへ行ってHUNになったときかされた。
前述のウルトンバートル教授は、このことについてフンというのはモンゴル語でいう人のことです、といった。
ね、古代、漢人が草原で匈奴に出遭った。そのように想像しなさい、とウルトンバートルさんはいう。
匈奴は、馬に騎(の)っています。漢人がたまげて、あなたは何であるかと問いました。これに対し匈奴は馬
上から、自分は人(フン)である、と答えたのです、それが、民族の名称として一般化したのです、とこの人は
いった。
モンゴル語でのフン(人)は文語ではフムンになり、フンヌに音が似ているのである。
(文庫P22〜23)
ついでながら、中国人の表記ではハンガリー(1)のことを、匈牙利と書くのである。(日本でも明治・大正ごろ
はそれを借用していた)(略)現代中国語では匈はxiongという音で、匈牙利と書くとションヤリーになってしま
い、実際の国名とかけはなれてしまう。(その欠点から、最近、洪牙利(ホンヤリー)という表記に変える場合も
あるらしい)ともかくも、それでも匈の字を使いたがったあたりがおもしろい。
おそらく、清(シン)末、世界の国名の漢字表記をきめるにあたって、英記のHUNGARYを基礎としたにちが
いなく、そのとき−想像だが−傍(かたわ)らの英国人が、これはフン族の国だ、と清国人に教えたのではない
か。フン、すなわち−とその英国人が−貴国の古典に現れる北方民族の匈奴(きょうど)のことだ、とでも教え
ねば、わざわざ清国人が音(おん)の異なる匈という字を当てるはずがなかった。
(文庫P29〜30)
[注]
(1)「フン族の地」の意。しかしこれは、匈奴とは別種のアジア系遊牧騎馬民族であるマジャ−ル人が建てた国。
それが、アッティラ大王の率いたフン族の帝国の故地にできたため、ヨーロッパ人が混同してしまったことに
よる国名。
草2 モンゴル帝国2代オゴタイ=ハンが建設した都 「カラコルム」
ついでながら、カラは、黒い砂地(カラ・コルム)のカラ(kar)である。モンゴル語とおなじ語族のトルコ語もカラ
(kara)は黒である。
日本語でクロというのは、ひょっとすると偶然ではないのではないかと私は学生時代おもっていたし、いまも、
クロという、日本語にしては強すぎる発音を何度かくりかえすと、つい鼻腔(びこう)にユ−ラシア大陸のにおいが
ひろがってくる。
(文庫P60)
草3 ヨーロッパ人に中国と誤認された、モンゴル系契丹(きったん)族の征服王朝 「契丹(=遼)」
しかも民族としては、おかしなことに契丹はモンゴル民族なのである。ただ、漢化した。
漢化したために、生(き)のままのモンゴル人たちは、契丹人に異質を感じ、からかって(?)漢人あつかいにする
うちに、契丹をもって漢人そのものを指すようになったのかもしれない。(略)
中国のことを“契丹”とよぶモンゴル人の誤認はそのままロシア語にひきつがれ、ロシア語では、いまなお中国の
ことをキタイとよぶ。
この誤認はさらにヨーロッパ語にまで及び、カセイ(英語の文語の Cathay )というよび方になった。要するに契丹
のことである。
(文庫P112〜114)
草4 中国東北部に列強がつけた呼び名 「満洲(=満州)」
ただ、漢人からみれば、王朝そのものが夷(えびす)であった。このため清王朝にあっては自分たちがかつて女真
とよばれていたことさえ気に入らず、みずからの民族名は満洲(マンジュ)であるとした。
要するに民族名であり、清朝がその故地のことを満洲とよんだことはない。東三省(とうさんしょう)、あるいは単に
東省と称した。
が、清末の十九世紀になって、列強がこの老帝国と接触するにおよび、欧米人の側がどうまちがったのか、その
地のことを、
「Manchuria 」
とよんだ。この呼称が明治の日本に−いわば西欧経由で輸入されて−満洲とよぶようになった。
(文庫P131〜132)
草5 日本の「満州」駐屯(ちゅうとん)部隊 「関東軍」
清朝がその故地をよぶとき、もうひとつのよび方があった。
「関東」
というものだった。長城の関所である山海関から東という意味で、近世日本において箱根の関所から東のことを
関東とよんだのに似ている。清朝の場合、関東三省(奉天省・吉林(きつりん)省・黒竜江省)とよぶこともあった。
これによって、日露戦争のあと、日本は満洲に駐屯(ちゅうとん)させた小さな部隊のことを、正称として、
「関東軍」
とよぶようになった。満洲と関東が、地名として併用されたことになる。
(文庫P132〜133)
[注]
(1)ポーツマス条約によって租借した遼東半島(満州の南端)に置かれた守備隊。
